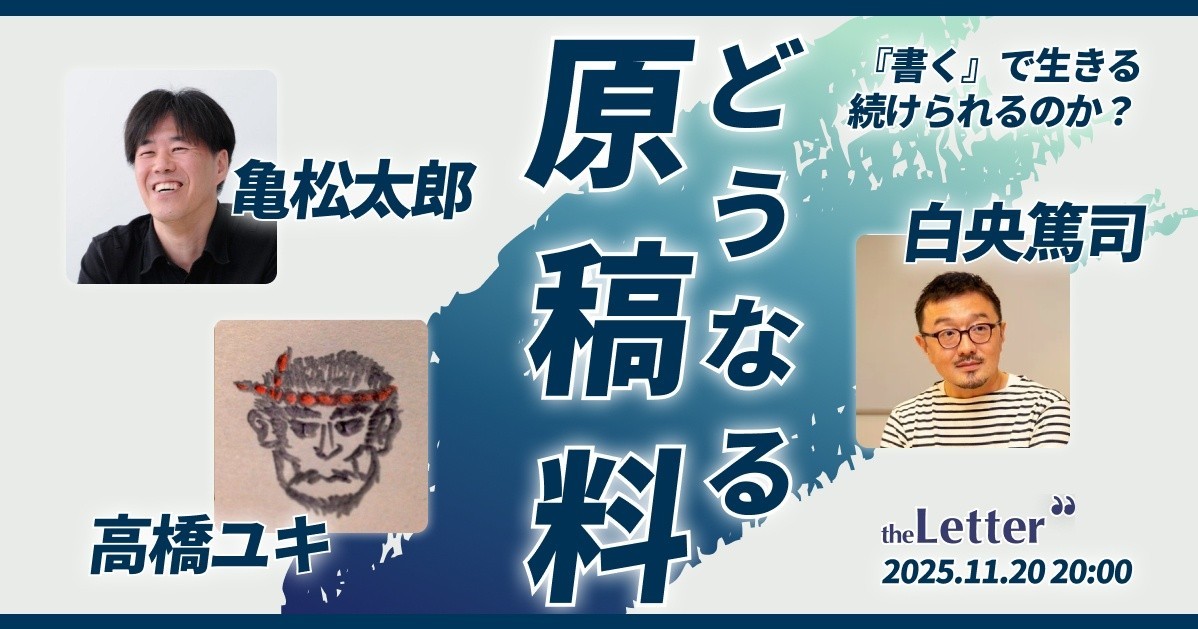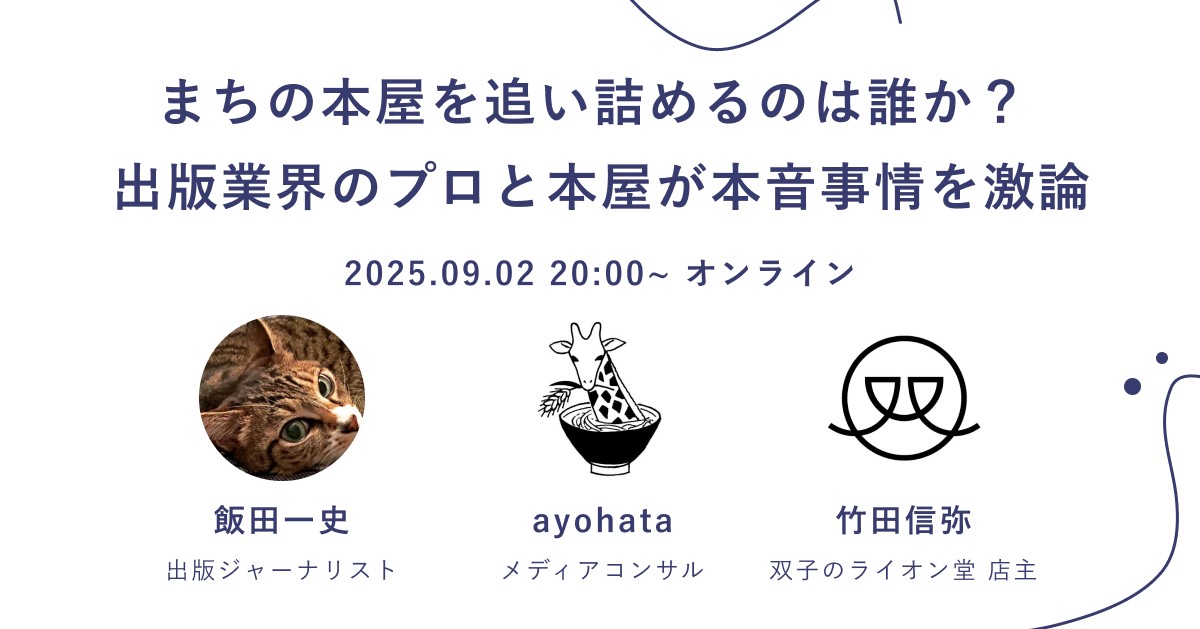あえて読者を絞りtheLetterで “本音発信”を続けるのはなぜ? 産婦人科医・重見大介さんに聞く、継続的な情報発信の「価値」と「適材適所」
theLetter ストーリーは、theLetter 上で活躍する書き手の方々に、メディア運営方法や活用の理由などを深掘りする公式ニュースレターのコーナーです。
「産婦人科 × 公衆衛生」をテーマに、医師と事業家の両面で活動している重見大介さんは、theLetter を利用し「産婦人科医・重見大介の本音ニュースレター」を運営しています。今回は、本音で書き綴ったニュースレターを通して熱量の高い読者と信頼関係を築くための考え方、事業運営や講演活動などに与える影響について伺いました。

情報発信に力を入れるのは、社会課題と向き合うため
もともとは産婦人科医として診療を中心に活動していましたが、今はベンチャー企業で遠隔医療、具体的にはオンライン相談の事業運営に携わっています。それと並行して、産婦人科の病気や性教育に関する講演など、女性の健康と社会課題を掛け合わせた取り組みもしています。
学生時代の病棟実習で、生き生きと働く産婦人科の先生方に惹かれ、産婦人科に進むことを決めました。手術も外来も出産の立会いもあり、忙しいながらもやりがいがありそうだと感じたんです。
専門医として患者さんを多く診るようになると、より質の高い医療を提供したいと考えるようになり、最新の論文を読んで臨床に活かすために公衆衛生大学院へ進学することにしました。
大学院進学後、視点が大きく変わりました。私はこれまで個々の患者の治療計画に集中していましたが、大学院の仲間たちは「社会全体の健康」に目を向けていたのです。最初は衝撃でしたし、戸惑いもありましたが、こうした議論を日常的に行う中で、診療の枠を超えて急激な少子化や年間十数万件の妊娠中絶といった社会課題と向き合う必要性を感じました。
そこから、遠隔医療の事業運営に携わり、情報発信にも力を入れて取り組むようになりました。
継続的な情報発信の価値は「リアルな情報収集」と「信頼のストック」
情報発信には、「伝えるべきことや人々が必要としている情報を届ける」という目的以外にも大きなメリットがあります。
ひとつは、発信を通じて患者さんのリアルな声に触れられることです。発信すると、シェアやコメントなどのリアクションが返ってきますよね。特に、医者が普段接することのない、患者さんの本音や切実な声を知ることができるのが大きいです。
診察室では、患者さんは愚痴を言いづらいですし、そもそも「病院で嫌だった経験」は直接私たちには伝わってこない。でも、SNSなどで発信すると、「こういう経験が嫌だった」「先生にわかってもらえなかった」といった反応が届く。そういった意見があることを知れるだけでもすごく勉強になりますし、事業の方向性を考えるうえでもとても役立っています。
もう一つ、情報発信を続けることで「この人の言うことは信頼できる」と思ってもらえるのも大きなメリットです。発信を続けることで私個人への信頼が積み重なり、それが事業への関心や受け入れやすさにつながっていると感じます。theLetter は昨年プロ・専門家向けの執筆プラットフォームにリブランディングしているので、よりそういった側面が強まったのではないでしょうか。
やりたいことがある方は、まず発信を通じて信頼を蓄積しておくと、いざ実行するときに大きな後押しになるのではないかなと思います。特に専門性のある分野では、質の高い発信を継続的に行うことで「この人の話なら聞いてみたい」と思ってもらえるようになると実感しています。
読み手との関係値から適切な発信場所を選ぶ
ネットでの情報収集がメインとなった今では、様々な発信サービスがありますが、産婦人科というセンシティブな領域にフィットする場所は少なく、SNSやメディアでの発信に課題を感じていました。そうした中でtheLetterを選んだのは、一定の関心を持った読者に向けて発信するので、誤読が起きづらく、書き手としての心理的安全性が保たれる点に惹かれたからです。
さらに、無料の購読者と有料のサポートメンバーを分けて発信できるので、より個人的な思いやセンシティブな内容も安心して書ける。こうした他のプラットフォームにない細やかなコントロールができるので、今も安心して発信を続けられています。
今のSNS環境では、産婦人科の話題を発信するのがなかなか難しいと感じています。妊娠や出産、不妊治療といったテーマは、多くの人にとってセンシティブな問題ですよね。当然、配慮が必要ですし、よく考えてから発信するようにしています。
以前、子宮移植について医学的な視点で紹介したことがあるのですが、「子宮を物のように扱っている」といった反応が寄せられました。もちろん、研究の詳細や背景を知らない中での意見なので仕方ない部分もありますが、SNSではそういった誤解や強い反応が生まれやすいと改めて実感しました。医学的に意味のあることを伝えるのが目的でも、受け取る側の背景によってはまったく違う意味に受け取られることもあります。
その点、theLetter は読者の方々と前提が揃っているので、自分が本当に書きたいことを自分の言葉で素直に発信しやすいです。大手メディアに寄稿する場合も、自分の言葉で書けますが、読者の反応はほぼ見ることができません。トレンドに載るとシェアされているのはわかるものの、ダイレクトなリアクションは得られない。SNSは拡散力がある分、意図しない受け取られ方や誤解も生まれやすい。
theLetter は登録してくれた読者に向けて発信でき、直接的なやりとりも可能なので、発信者として安心感があります。私の場合、サポートメンバーに向けたYouTubeライブ配信などのイベントと絡めて読者と直接交流する機会もあり、theLetter を軸にいくつかの発信プラットフォームと組み合わせた形がうまく機能しているように思います。
可視化された信頼の蓄積はやりがいに
SNSのフォローという仕組みは「フォローをする=信頼している」とも限らず、それ以外のメディアでは、読者がどれほど関心を持っているかを把握しづらいものです。特に、単発の記事発信は、その時のトレンドや出版社の広報に大きく左右されてしまいます。
theLetter では、読者数の増加や記事の開封率、シェア後のPVなどを管理画面で可視化できるため、大きなやりがいを感じます。記事を配信したり、SNSで紹介したりしたときに、うまく拡散されると登録者が増えるのがリアルタイムでわかる。そういった手応えがあると、「もっと読者の方に役に立つ記事を書いていこう」と思えるので、いい循環が生まれていると感じますね。
例えば、先日行ったアンケートの結果をご紹介すると、ニュースレター登録理由(複数回答可)の上位は「記事の質が高そうだった」(77%)、「配信者が信頼できそうだった」(72%)、「他では読めない情報が多そうだった」(58%)でした。
フリーコメントでも「安心して妊婦生活に必要な情報を得ております」「性教育について大人になった自分も救われています」などの声もダイレクトにいただけました。
産婦人科の領域はセンシティブな内容なので、インターネット上で踏み込んだ”本音”の発信はあまり見かけません。さらに、一般の方がその情報の正しさを判断することは難しい。だからこそ、専門家の本音と正しい情報を伝えることへの期待を感じますし、信頼して登録してくださった方へ応えられるよう、できる限り有益な情報を届けたいと考えています。
熱心な読者からの反応は、想像以上に執筆のモチベーションにつながります。読者から直接、自分を突き動かすエネルギーをもらえることも、theLetterならではの魅力ですね。
後編:「約1万人の熱量の高い読者が集まる、theLetterを軸とした発信サイクルの構築方法」に続く
theLetter の運営と一度お話してみたい、どんなサービスなのか詳しく知りたい、事例を聞きたい、などご興味お持ちの方は以下のボタンから「theLetter ご利用相談フォーム」よりサポートすることが可能です。
引き続き、利用者の皆さんと theLetter の改善をすすめてまいります。
すでに登録済みの方は こちら